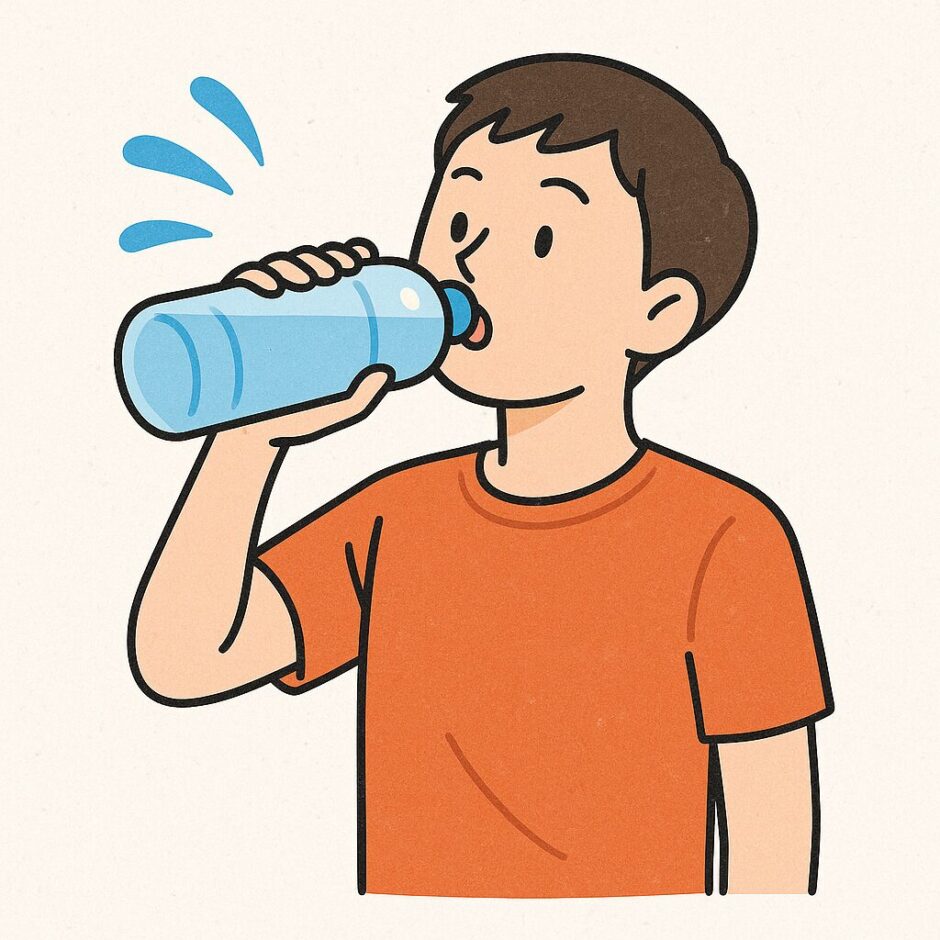——たくさん飲めばいいわけじゃない。“自分の身体の声”を聞くことから始めよう
「水は1日2リットル飲みましょう」
——そんなフレーズを、あなたも一度は聞いたことがあるかもしれません。
ボトルを持ち歩いて、タイマーで水分補給を管理する。
“水を飲むこと”が、健康の象徴のように扱われる時代になりました。
けれど私は、医師としてこう伝えたいのです。
「水は“たくさん飲めば健康になる”わけではありません」
「あなたにとっての適量を、あなた自身の感覚で見つけてほしい」
この記事では、
・“1日2L神話”の真実
・医学的に必要な水分量の目安
・こまめな水分補給のコツ
・水と“体調”の微細な関係性
などを掘り下げながら、あなたと水との距離を少しだけ見直すきっかけを届けたいと思います。
■ 「1日2リットル」は、誰にでも必要なのか?
まず、よくある“健康情報”として言われるのが、
**「1日2Lは飲みましょう」**というフレーズです。
もちろん、間違いではありません。
でも、“全員に2Lが必要”ではないということが、とても大切です。
実際には、
- 年齢
- 体格
- 活動量
- 食事の内容
- 気温・湿度
といった生活環境や体調によって、必要な水分量は大きく異なります。
📊 一般的な水分摂取の目安
以下は、「ふつうに生活している人」が1日に必要とされる水分量の目安です。
● 通常の生活環境
→ 1.2〜1.5リットル程度(水やお茶などから)
→ 食事に含まれる水分も合わせて、合計約2L弱
● 発汗が多い・運動時・発熱時など
→ 通常に加えて +500〜1000ml
これは、あくまでも“目安”であり、
本当に必要なのは、「喉の感覚」や「尿の色」などから自分の状態を感じる力です。
■ 水分が不足すると、体には何が起こるのか?
水分が足りなくなると、まず現れるのは「喉の渇き」ですが、
それ以外にも体はさまざまなサインを出してきます。
🔻 水分不足のサイン
- 頭がぼんやりする・集中できない
- めまいや立ちくらみ
- 尿の色が濃くなる
- 肌や唇が乾く
- 便秘になりやすい
体の60%以上は水分で構成されています。
わずか1〜2%の脱水でも、パフォーマンスや体調に影響を及ぼすことがわかっています。
つまり、「喉が渇いた時点ですでに軽度の脱水」。
だからこそ、「喉が渇く前に、少しずつこまめに」が大切なのです。
■ 医師が勧める「こまめな水分補給の習慣」
無理にたくさん飲む必要はありません。
でも、“忘れず、こまめに”飲む習慣を身につけるだけで、体調が大きく変わる人も多くいます。
⏰ 1. 朝起きてすぐの1杯
→ 寝ている間に500ml〜1Lの水分が失われると言われています。
→ 朝イチの白湯や常温の水は、腸もやさしく起こしてくれます。
💻 2. 仕事中は1時間に1回、少しずつ
→ 机に水を常備して、「一気に飲まず、数口ずつ」が理想です。
🍵 3. 食事中・食後にも1杯
→ 食事の水分と合わせて、水分補給としてカウントできます。
🛁 4. 入浴前後の水分補給
→ 入浴時も汗で意外と水分が失われています。
→ 湯上がりの冷たい水は、体に染み渡るような快感です。
🌙 5. 就寝前に少しだけ
→ 脱水を防ぎつつ、夜間トイレが近くならない量(50〜100ml)が◎
■ 「水を飲む=健康」ではない
世の中には、“水を飲めば痩せる”“美肌になる”といった情報が溢れています。
確かに、水分が体調に与える影響は大きい。
でも、**「水を飲んでいるから健康」ではなく、「自分の体調を感じ取れているから健康」**という視点を、私は大切にしています。
たとえば:
- 今日は汗をかいたから、もう少し多めに飲もう
- なんだかぼーっとするな。水分が足りないかも?
- 飲みすぎてお腹が張っている。ちょっと減らそう
こんなふうに、身体と“会話”するように水を飲むことが、実は最も健康的な習慣なのです。
■ 飲みすぎにも注意!「水中毒」というリスク
意外と知られていないのが、**“水の飲みすぎによる健康リスク”**です。
大量の水を一気に摂取すると、
血液中のナトリウムが薄まり、「低ナトリウム血症」と呼ばれる状態になることがあります。
症状としては:
- 頭痛
- 吐き気
- めまい
- 意識障害
ときには命に関わることもある、“水のとりすぎ”のリスク。
特に運動直後や高齢者は注意が必要です。
“適量”を“こまめに”が、やはり鉄則です。
■ Truvitaが目指す「水とのつきあい方」
Truvitaでは、医師との定期的な対話を通して、
“水を飲む”という行為すらも、「自分らしい健康習慣」としてデザインしていきます。
たとえば:
- 水分量と体調変化の記録
- 便秘やむくみの相談
- 利尿剤や糖尿病薬を使用している方への水分管理指導
- 高齢者の脱水予防と、飲みやすい工夫の提案
“水を飲む”という、当たり前でささやかな行為。
けれどそれを、“医療と信頼で支える”というアプローチは、これからの時代にこそ必要だと感じています。
■ 最後に:「喉が渇く前に、体の声を聞く」
健康のために水を飲むことは、とても大切です。
でも、
「飲まなきゃ」と無理をしていたり、
「飲めていない」と自分を責めていたりするなら、
それは本来の“健康のため”とは、少し違うかもしれません。
“体の声に気づくこと”こそが、最もやさしくて確かな健康習慣。
毎日のなかで、ふと一口水を飲んだとき、
「あ、自分は今日、少し疲れてたんだな」と気づける。
その感覚を、大切に育てていきませんか。
—— Truvita
 ~The Bespoke Medical Survice For Your Life~
~The Bespoke Medical Survice For Your Life~