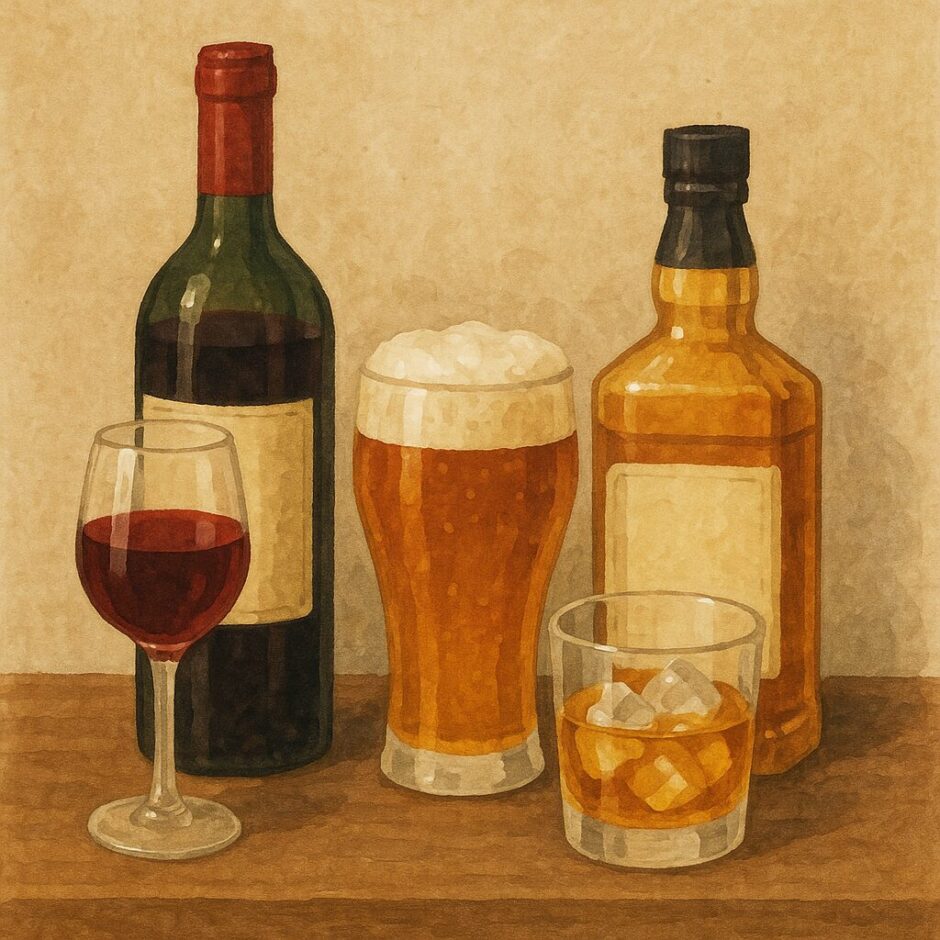——本当に見つめ直すべきは、“飲む理由”かもしれない
「最近飲みすぎてる気がするけど、やめられなくて……」
「お酒が好きって言うと、すぐ“身体に悪い”って言われるんです」
そんな声を、診察室でよく耳にします。
お酒——それは人との会話を弾ませ、気分を高め、日常に少しの彩りを添えるもの。
ときには、孤独や不安をなだめ、疲れた心をふっとゆるめてくれる存在でもあります。
でも同時に、**“体に悪いもの”“習慣性があるもの”“やめるべきもの”**といったレッテルも、しばしば貼られてしまうのが現実です。
本当に大切なのは、**「飲むか/飲まないか」ではなく、「なぜ飲むのか」**という問いです。
医師として、そして人間として。
私は、お酒との付き合い方を“ジャッジする”のではなく、“理解する”ことから始めたいと思っています。
本稿では、アルコールの医学的な影響だけでなく、心との関係、生き方とのバランスについても掘り下げていきます。
■ お酒は“毒”か? “癒し”か?
アルコールは、医学的には明確に「発がん物質」とされます。
実際、過度の飲酒は以下のような健康リスクを高めることが知られています。
・高血圧
・脂肪肝、肝炎、肝硬変
・食道がん、口腔がん、大腸がん
・うつ病や不安障害の悪化
・睡眠の質の低下
しかし——
これらのリスクは、「適量を超えた飲み方を続けた場合」の話です。
つまり、**“お酒が悪い”のではなく、“付き合い方に問題がある”**ということ。
■ 適量とは何か? 医学的な基準から
では、“適量”とはどのくらいなのでしょうか?
📊 厚生労働省などが示す1日の純アルコール摂取量の目安は「20g程度」
これは、以下の量に相当します:
- ビール(5%):中瓶1本(500ml)
- 酎ハイ(7%):缶1本(350ml)
- カクテル:2杯程度(計350ml)
- 日本酒:1合(180ml)
- ワイン:グラス2杯(計200ml)
- ウイスキー:シングル2杯(計60ml)
※ただし、体格や性別、肝機能の個人差によって許容量は変わるため、絶対的な基準ではありません。
「思ったより少ない……」と感じた方もいるかもしれません。
でも重要なのは、「量より“意味”」です。
■ なぜ飲むのか?——心が求めるアルコール
医療現場で私が注目しているのは、
**「どんなときに、どんな気持ちで飲んでいるか」**という点です。
たとえば:
- 嫌なことがあった夜に、気分転換で飲む
- 不安で眠れず、寝酒に頼る
- 仕事のストレスから逃れるために飲む
こうした“心の逃げ場”としての飲酒が習慣化すると、
本来向き合うべき問題が見えづらくなるのです。
逆に、
- 食事を楽しむため
- 人との会話を豊かにするため
- お祝い事のひとときを演出するため
という“ポジティブな目的”であれば、
お酒は人生に彩りを添える素晴らしいパートナーになります。
■ 飲酒と「眠り」の誤解
「お酒を飲むと眠れるんです」
という方はとても多いです。
確かに、アルコールには入眠を促す作用があります。
しかし実は——
**アルコールによる睡眠は、“質”が悪い”**ということが、数多くの研究でわかっています。
- 中途覚醒が増える
- 睡眠の深さが浅くなる
- レム睡眠が抑制され、夢を見る頻度が低下
つまり、**“寝た気がしない眠り”**を毎晩繰り返してしまうことに。
もし「寝つきのために飲む」が日常化しているなら、
見直すべきはお酒ではなく、生活リズムやストレスケアそのものかもしれません。
■ 「やめる」のではなく、「選ぶ」飲み方へ
私は医師として、無理にお酒をやめさせようとは思っていません。
大切なのは、
「その一杯が、自分を元気にするのか?」
「その一杯が、何かから逃げるためなのか?」
——この問いに、正直に向き合うことです。
お酒を“敵”とみなす必要はありません。
でも、お酒に“依存”するような人生には、どこかでブレーキをかける勇気が必要です。
■ 医療は、数字を整えるためにあるのではない
血液検査のγ-GTPが高い。
肝機能の数値が基準を超えている。
もちろん、それは“医学的には”問題かもしれません。
でも私が大切にしているのは、
**「あなたの人生が、健康に支えられているかどうか」**です。
医療とは、「数値をよくすること」ではなく、
「生き方そのもののバランスを取り戻すこと」。
そのためには、お酒だけを見直しても不十分で、
・仕事のペース
・家庭での役割
・心の癒しの方法
——そういった“暮らし全体”を見つめ直す必要があります。
■ Truvitaの取り組み:お酒との関係も、人生の一部として
Truvitaでは、
お酒を「やめるか、続けるか」だけで判断するのではなく、
**「どんな生活の中で、それが存在しているのか」**を大切にしています。
たとえば:
- 定期的な肝機能チェック
- 飲酒日記の提案
- 眠りとの関係性の可視化
- ストレスの根本にある要因の整理
こうしたアプローチによって、
“お酒に飲まれる”のではなく、“自分で選ぶ”飲み方をサポートします。
■ 最後に:あなたとお酒の距離を、見直してみませんか
「今日も一杯やろうかな」
その気持ち自体を、私は否定しません。
ただし、その一杯が:
- 習慣でなんとなく飲んでいるものなのか
- 心のSOSに気づけていない証拠なのか
- 本当に味わいたいと感じているものなのか
を、たまには立ち止まって考えてみてほしいのです。
お酒は、人生の“調味料”のような存在。
でも使い方を間違えると、味そのものを壊してしまうこともある。
「飲む or 飲まない」の二択ではなく、
「どう飲むか」の選択を、あなた自身ができるように。
そのお手伝いを、私たちは“医療”という立場から、そっと支えていきたいと思っています。
—Truvita
 ~The Bespoke Medical Survice For Your Life~
~The Bespoke Medical Survice For Your Life~