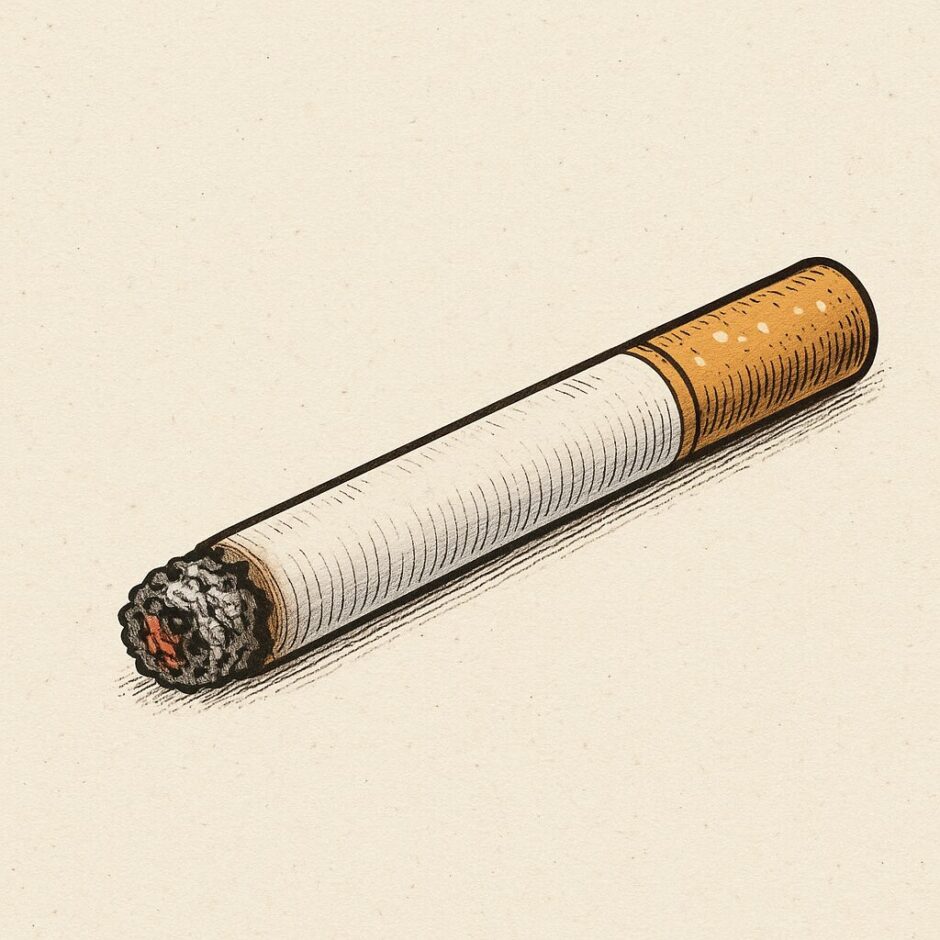🚬 タバコと健康に関する考察 〜やめることより、向き合うこと〜
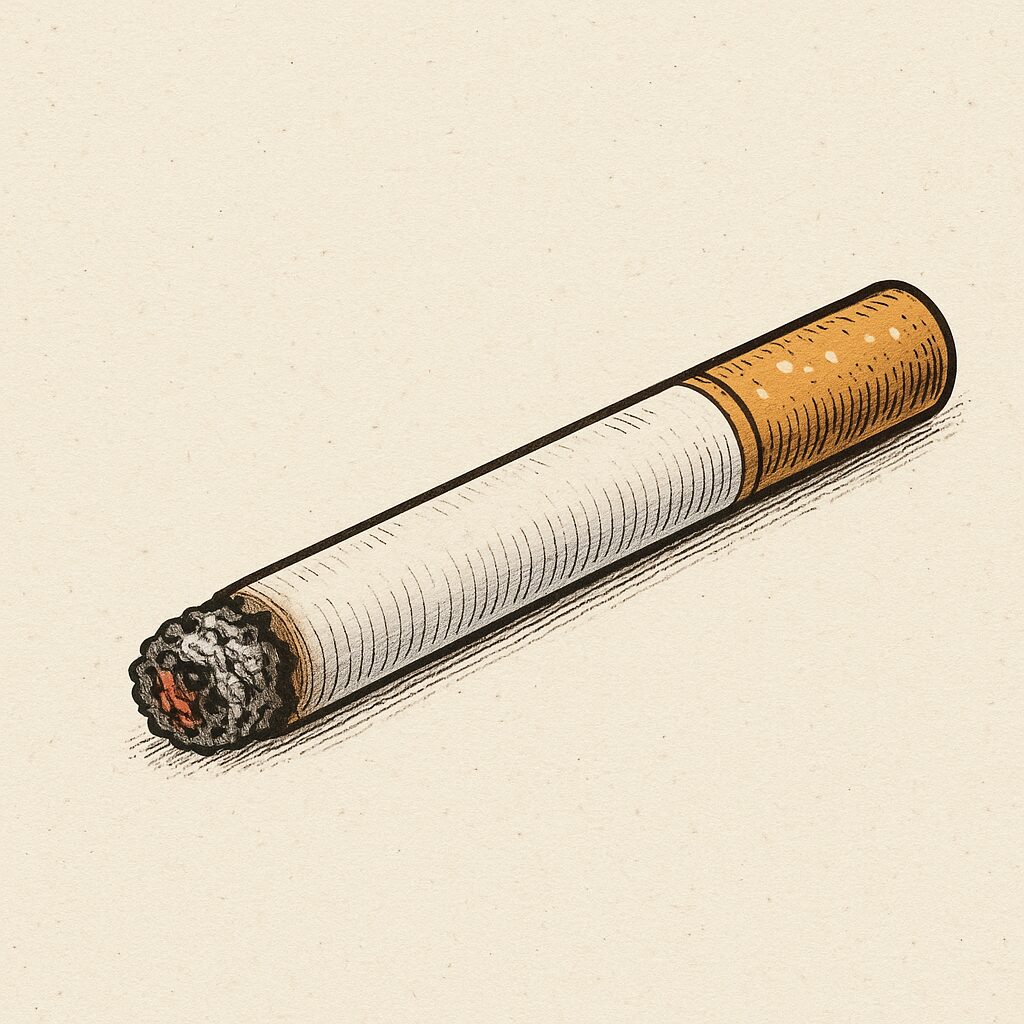
「まだタバコ吸ってるの?」
そう言われるたびに、肩身の狭い思いをしている人がいます。かつては社交の一環として、あるいはリラックスの手段として受け入れられていた喫煙が、今では多くの場面で“忌避されるもの”となりつつあります。
しかし、医療の立場から私はこう思います。
「タバコを吸うことが悪い」のではなく、
「吸わずにはいられない理由」にこそ、耳を傾けたい。
これは単に禁煙を勧めるという話ではありません。
むしろ、“吸っていることそのもの”に意味や背景があるのだとすれば、それを無視したアドバイスは、何の役にも立ちません。
本稿では、医学的な知見と実際の臨床経験を交えながら、「タバコと健康」について深く掘り下げていきます。
■ 喫煙の健康への影響 〜1日1本でも、危険はある〜
まず事実として、喫煙による健康リスクは、非常に高いものです。多くの人が誤解しているのは「本数を減らせば安全になる」という考えですが、実際には“1日1本”であっても以下のような影響が報告されています:
- 心筋梗塞のリスク:約1.5倍(非喫煙者に比べ)
- 脳卒中のリスク:約2倍
- がん全般、特に肺がん・食道がん・膀胱がんなどの発症率も有意に増加
さらに、喫煙は“慢性的な炎症”を引き起こし、動脈硬化、高血圧、糖尿病の悪化などにも関与します。つまり、喫煙は「単独で悪い」のではなく、「すべての病気のリスクを底上げしてしまう」要因なのです。
■ ニコチン依存は「意思の弱さ」ではない
ここで誤解してはならないのが、「吸ってしまうのは本人の意志が弱いからだ」という偏見です。
ニコチンには強い依存性があり、摂取すると数秒で脳に作用して快感物質(ドーパミン)を放出させます。これはアルコールや一部の薬物と同様の“報酬回路”を刺激するため、やめることは「努力」で解決するものではありません。
実際、喫煙者の多くが「本当はやめたい」「やめる努力をしてきた」と話します。医師として大切なのは、この葛藤に対して共感を持ち、“依存症としての治療”を視野に入れていくことです。
■ 禁煙の効果 〜1年で心臓、5年で脳、10年でがんのリスクが下がる〜
「もう手遅れでは?」と思われがちですが、禁煙はいつ始めても意味があります。
- 禁煙1ヶ月:咳や痰、息切れが軽減し始める
- 禁煙1年:心筋梗塞・狭心症のリスクが半減
- 禁煙5年:脳卒中や口腔がんなどのリスクが半分以下に
- 禁煙10年:肺がんのリスクが、非喫煙者の水準に近づく
医学的には、禁煙を始めたその日から、身体の回復は確実に始まります。つまり、“まだ吸っている今”こそが、変化の起点になり得るのです。
■ 医療の役割は、「禁煙指導」より「伴走」
医師は「やめましょう」と指導する立場にあると思われがちですが、私は少し違うと考えています。
本当に必要なのは、「どうやってやめるか」ではなく、
「なぜ吸っているのか」「やめた先に何があるか」を一緒に考えること。
たとえば、喫煙が:
- ストレス対処の手段である場合
- 孤独や不安を紛らわす習慣である場合
- 自分だけの“リセットスイッチ”である場合
それを無理に奪うのではなく、「代わりにできること」を一緒に探していく。医療とはそういうものであるべきだと思っています。
■ Truvitaの立場から
私は、専属主治医契約サービス“Truvita”を通じて、「病気を診る」だけでなく、「人と暮らしを診る医療」を目指しています。
タバコをやめるかどうかは、その人の選択です。けれどその選択が、「孤独のなか」ではなく、「信頼のなか」で行われるように。
あなたが健康について悩んだとき、迷ったとき、
「まずこの人に相談しよう」と思える医師でありたいと思っています。
— Truvita
 ~The Bespoke Medical Survice For Your Life~
~The Bespoke Medical Survice For Your Life~